産休・育休時には給付金がもらえたり保険料が免除になったりします。
普通の会社なら、妊娠の報告をすれば担当窓口で各手続きを行ってくれると思います。
しかし会社側のミスで抜け落ちることがあることも考えられるので、自分でもどんな手当や制度があるのか把握しておく必要があるかと思います。
私は少人数の企業で働いていて、産休・育休を取得した初の社員となりました。
出産に関わる申請は会社で手続きしてもらいましたが、申請が漏れていたものがあったので、その時自分で調べたことをまとめてみました。
もらえる給付金
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 育児休業給付金
これらを詳しく見ていきます。
出産育児一時金
申請先は健康保険組合です。会社がどの健康保険組合を使っているかは、お持ちの健康保険証で確認してください。
出産すると一児につき42万円支給される制度です。
申請方法には、
- 直接支払い制度
- 受取代理人制度
- 事後申請
の3つの方法があります。
私は第1子の時に直接支払い制度、第2子の時は受取代理人制度を利用しました。
直接支払い制度
出産育児一時金を自分では受け取らず、直接病気に支払う制度です。
大きな病院なら大体申請できるそうです。
申請方法は、病院に保険証を提示して書類に記入して提出します。
病院に支払う入院費などの出産費用が42万円以上の場合は、退院時に差額を病院に支払います。
42万円以下の場合は、健康保険組合に申請すれば差額が戻ってきます。
受取代理人制度
本人が受け取らず直接病院に支払えますので、直接支払い制度と変わらないように見えますが、病院と健康保険組合とのやりとりが少し違うようです。
直接支払い制度を導入していない小さな病院だとこの方法になる場合が多いようです。
最初の申請方法も少し違っていて、自分で申請書類を用意します。(会社の担当窓口でも用意してくれる場合もあるそうです。)
私は健康保険組合のHPから申請書類をダウンロード、プリントアウトしました。
書類に記入したら、健康保険組合に提出します。
私は郵送で提出しました。
事後申請
直接支払い制度、受取代理人制度を使わないで、全額自分で受け取ることもできます。
その場合は、病院で全額自費で支払い、後で申請して出産育児一時金を受け取ります。
病院がクレジットカード支払いに対応していれば、ポイントがつくなどのメリットがあります。
出産費用は結構な金額になるので、クレジットカード支払いに対応していれば、この方法でも良かったなと今となっては思っています。
出産手当金
産前6週間(42日)と産後8週間(56日)に会社を休むことを産休といいます。
この期間にもらえる給付金が出産手当金といい、これも健康保険組合に申請します。
もらえる金額は、普段もらっている給料や、産前産後休暇の期間により変わってきます。
下記のサイトでは出産予定日から産前産後休暇や育児休暇、貰えるお金を計算できます。
【2021年最新版】産前産後休業・育児休業給付金|期間・金額計算ツール
ご出産予定の方のために、出産予定日などの情報をご入力いただくと「育児休業・産前産後休業の期間」だけではなく「給付金・手当の概算金額」なども自動計算するページです。また、必要な申請手続きや給付金・手当が支給される時期もご紹介しています。このページは東京都千代田区の社会保険労務士法人アールワンが提供しています。
申請の手順は以下の通りです。
- 会社の担当窓口か健康保険組合のHPから「健康保険出産手当金支給申請書」を入手する
- 必要事項を記入
- 出産後の入院中や、退院後に来院して医師・助産師記入欄を担当医や助産師に記入してもらう
- 勤務先に提出し、事業主の記入欄に記入してもらい、健康保険組合に提出
申請から振込まで1〜2ヶ月ほどかかります。
育児休業給付金
母親は産後8週後から、父親は産後すぐから育児休業が取れます。
その場合支給されるのが育児休業給付金です。
これは雇用保険から支払われ、申請先は会社の所在地管轄のハローワークになります。
支給期間は赤ちゃんの1歳の誕生日までですが、保育園などに入れないなどの理由で復職できない場合は1歳半まで、2歳まで、と段階的に延長できます。
こちらも育児休業給付金は月給によって支給金額が決まりますので、このサイトで計算してみてください。
【2021年最新版】産前産後休業・育児休業給付金|期間・金額計算ツール
ご出産予定の方のために、出産予定日などの情報をご入力いただくと「育児休業・産前産後休業の期間」だけではなく「給付金・手当の概算金額」なども自動計算するページです。また、必要な申請手続きや給付金・手当が支給される時期もご紹介しています。このページは東京都千代田区の社会保険労務士法人アールワンが提供しています。
申請方法は、必要書類を会社所在地管轄のハローワークに提出します。
自分でも申請できることができます。
私は自分で申請しましたが、かなり面倒です。
理由としては、
- 2ヶ月に一度、給付の申請書を出さないといけない
- 事業主に記入してもらう箇所があるため、書類を会社に持っていくか郵送しないといけない
- 会社所在地管轄のハローワークに提出するので自宅から遠い場合がある
- ハローワークへは郵送でも提出できるが、配達記録付きの返信用封筒を同封しないといけない
などの理由により、会社でやってもらった方がラクだと思います。
必要書類は下記となります。
申請者が用意するもの
- 母子手帳などの移写し
- マイナンバー(記入するところがあります)
※通帳の写しは令和3年8月より不要となりました
事業主が用意するもの
- 育児休業給付金支給申請書
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(雇用保険被保険者)休業開始時賃金月額証明書
- 支給申請書の内容が確認できる書類(賃金台帳、出勤簿 など)
2回目以降は、初回の受給資格確認手続き完了後に交付される「育児休業給付金支給申請書」と、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、労働者名簿、雇用契約書などを提出します。
免除になる制度
産休育休中は、健康保険と厚生年金の社会保険料納付免除の制度を利用できます。
雇用保険については、産休育休中は無給になるため発生しません。
手続き先は、厚生年金事務所です。
社会保険料の免除は、事業主を経由して「産前産後休業取得者申出書」や「育児休業等取得者申出書」を年金事務所に提出しますので、会社にお願いしましょう。
住民税は免除になる?
産休、育休中はだいたいが無給になると思います。
また、出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金は課税対象ではないため、この時期は住民税が発生しません。
しかし、住民税は納付の前年1月1日~12月31日の所得に対して計算され請求されますので、産休育休期間も収める必要があります。
産休育休中に自分で納付する方法や、復職後に給料から一括、または分割で支払う方法があるそうです。
私は復職後に給料から一括で支払いました。
こちらも会社の担当窓口で支払い方法を相談してみてください。
ちなみに支払いが難しい場合は、自治体によっては一定条件下で減免や猶予など特例措置を設けているそうです。
お住まいの自治体に問い合わせてみてください。
まとめ
出産前後は忙しく、ついつい手続き関連については後回しになってしまいますが、産休/育休中は給料が出ないことも多いのでこういった制度を使った方がいいと思います。
詳しくは、会社の担当窓口、健康保険組合、ハローワーク、年金事務所、自治体などに問い合わせてみてください。
参考URL
出産一時金の受取条件と申請方法を解説! 転職しても手続きできる? |女性の転職・求人情報 ウーマン・キャリア
出産育児一時金(以下「出産一時金」)は、公的医療保険に加入している被保険者、被扶養者が出産した場合、国から42万円の支給を受けられる制度です。支給条件や申請方法、受取方法などの各種手続き、退職・転職時の支給条件も紹介します。
出産手当金とは?計算方法や申請時期をわかりやすく教えます!|Like U ~あなたらしさを応援するメディア~【三井住友カード】
「出産手当金」という給付制度を知っていますか?働いている妊婦さんなら、勤め先で加入している健康保険に申請できますが、一体いくら受け取ることができるのでしょうか。そこで今回は「出産手当金」の計算方法や、申請時期などについて詳しく解説します。
【必見】育児休業給付金とは?申請・計算方法や延長できるケースまで、どこよりもわかりやすく解説|Like U ~あなたらしさを応援するメディア~【三井住友カード】
少子化の進行や女性の職場進出が進む現代、育児休業給付制度が制定されました。その制度の一つに「育児給付金」があります。この記事では、育児給付金の支給期間や申請方法、支給額の計算方法などをわかりやすく解説しています。
収入はゼロになるけど税金はどうなるの?産休・育休中の税金についてまとめました | 税金 | MONEY JOURNAL | 株式会社シュアーイノベーション
働く女性がめでたく妊娠し、産休と育休を取得した場合、原則として給与は支払われません。産休および育休で、労働者に与えられた「休業する権利」を行使しているからです。 しかし、給与がないにもかかわらず、納税義務のある税金があります。「どの税金をどう支払えばいいの」と不安な方もいらっしゃるでしょう。 そこで本記事では、産休や育休中に納めるべき税金や、社会保険料の支払い、配偶者の扶養に入る選択肢、出産関連費用の医療費控除などについてご紹介します。払うべき税金や納税方法だけではなく、利用できる優遇措置もわかるので家計のやりくりがしやすくなります。 この記事を読んで、「得するお金のこと」についてもっとよく知りたいと思われた方は、お金のプロであるFPに相談することがおすすめです。 マネージャーナルが運営す…






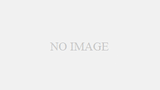
コメント